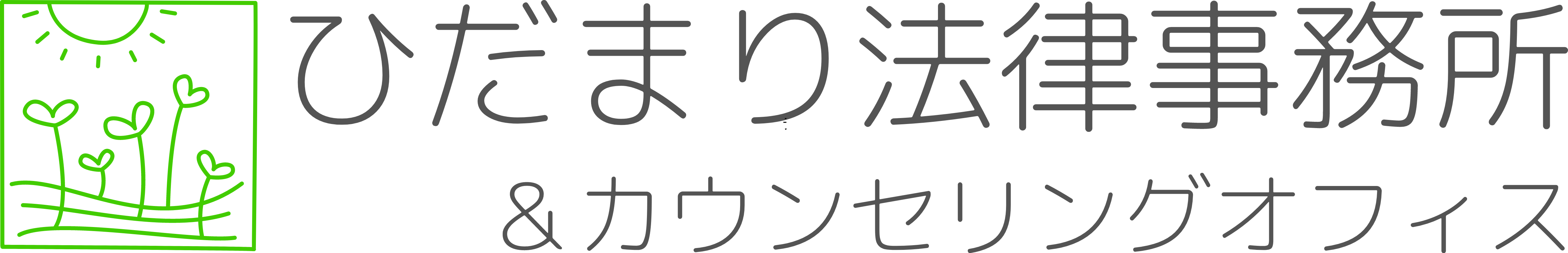1.ダルクに関わりはじめたきっかけ
弁護士になる前、ある裁判を傍聴した。法廷に立っていたのは、覚醒剤の事件で過去にも何度か刑務所に入っていた女性。今回、また覚醒剤を使って捕まったことで、子どもの入学式の日に一緒にいてあげられなかったと泣いていた。
当時、薬物依存症の知識のなかった僕は、覚醒剤は、悪い人が、違法な薬で楽しい思いをするために使うものだと思っていた。
でも彼女は、娘のことを思って心から悔いているように思えた。娘の入学式なんかどうでもいいから、違法な薬で快楽におぼれようとするような人にはどうしても見えなかった。子どもを大切に思っているお母さんが、子どものためを思ってもやめられない覚醒剤っていったいなんなんだろう?という疑問が自分の中にずっと残っていた。
その後、弁護士になって、覚醒剤を所持したり使用したりした人たちの弁護を何件も担当した。
警察署でアクリル板ごしに出会った人たちは、優しい人たちだった。そして、傷ついていたり、不安になったり、人が信じられなくなったりしていた。薬を使い続けたい人もいればやめたい人もいた。その人たちには、大切に思っている家族や仕事があった。そして、家族のためにやめるんだ、仕事に打ち込んでいれば薬は使いたくなくなるからもう大丈夫だと話してくれた。
でも、薬は止まらなかった。もう、この人たち自身の意思ではなんともならないんじゃないだろうか。もしかして、この人たちが苦しんでいるのは、この人たちのせいではないんじゃないだろうか。そう思って、自分にできることは何かないかと考え始めた。
でも、弁護人として関わった刑事裁判は、いつも茶番だった。
検察官は、この人は法律を守る意識がないから、刑務所で徹底した矯正教育を受けさせろと言う。
弁護人は、この人は反省していて、もう絶対使わないと誓っているから刑を軽くしろと言う。
裁判官は、覚せい剤を使わないという意思を強く持って、もう二度とやらないと約束しろと言う。
この法廷に、本当のことをしゃべっている人間は一人もいない。
全員が嘘つきだ。
だって、検察官は知っている。刑務所での矯正教育で薬は止まらないことを。弁護人は知っている。この人は前の裁判でも、もう絶対使わないと誓っていたことを。裁判官は知っている。もう二度とやらないと約束した人たちがまた裁判所に戻ってくることを。
その嘘つきたちが、被告人席に立つ人に嘘をつくことを強要する。
反省している、今はもう使いたいとは思っていない、家族のためにももう二度と使わないと言わせて納得する。
なんでこんな無意味な、いや、悪影響しかなさそうなセレモニーを繰り返しているんだろう?
僕は、こんな茶番じゃなくて、本当は何をすればいいのかを知りたかった。そしてダルクというものがあることを知った。
2.ダルクで、回復する人たちを見た
京都で弁護士を始めたが、2006年から故郷である香川に移った。香川は田舎だから覚醒剤の事件は少ないのかと思っていたが、そんなことはなく、どこでも覚醒剤は手に入るのだと知った。
そのころは、ダルクに行って回復する人がいることは知っていたから、覚醒剤の事件で捕まった人たちに警察署で会う度に、一人じゃやめられないですよ、ダルク行きませんかと話しかけ、ダルクの本やパンフレットを差し入れたりした。
みんな、釈放されたらダルクに行きますというけれど、実際にダルクにつながった人はほとんどいなかった。
覚醒剤を使ったこともない僕がそんなことを言ってみたって意味はないのだ。ダルクには、以前は薬物を使っていて、今はやめ続けている人たちがいる。その人たちが、僕の依頼者に会って話をしてくれたらいいのにな、とずっと思っていた。
香川ダルクの準備会が立ち上がり、大分からベンツさんが来てくれた。いろんな話をしてくれて、僕の依頼者の少年をミーティングに呼んでくれた。香川に少年のためのダルクを作りたいという夢を語ってくれた。
そのベンツさんは道半ばで亡くなられてしまったが、今も施設長の亨さんが香川に来てくれて、2011年に香川ダルクは始まった。
ダルクの立ち上がりは順風満帆ではなかった。
いろいろと問題はあったし、お金はなかったし、周りからの差別にさらされることもあった。
でも、ダルクには、薬物を使っている仲間たちが集まり、薬物を使わない今日一日を過ごしていた。そして、警察署や拘置所にいる人たちに会いにいって、メッセージを運んでくれた。香川ダルクの仲間たちが面会に行ってくれると、少しずつ話が伝わっていく感じがした。
以前は法廷で、僕も依頼者も、お互いに見え見えの嘘を、何度も何度もついてきた。
でも、香川ダルクの人たちが僕の依頼者に会いに来てくれて、僕の依頼者を仲間と呼ぶようになってからは、法廷で依頼者に、「今も薬を使いたい。やめられるかどうか不安だ。」と話してもらうことが増えた。
そして僕は、裁判官にこう言うようになった。
「もう二度と使いません、なんて見え透いた嘘じゃなくて、やめられないか不安だという本当の話が法廷でできるようになったのは、この人が本当に回復の道を歩き始めたからです。ここから早く出て、ダルクで仲間と過ごすことこそが必要です。刑務所にいくことはなんの効果もないばかりか、この人がダルクにつながろうとしているのを邪魔するという弊害しかないのです。」
僕は、法廷で嘘をつかなくても良くなった。
依頼者に嘘をついてもらわなくても良くなった。
僕は、自分の言葉を自分自身が信じられるようになってきた。僕の依頼者もそうだったかもしれない。そうだといいけど。
検察官はあいかわらず、「被告人は規範意識が鈍磨している。刑務所での徹底した矯正教育が必要だ。」なんていう嘘をついていたけれど、依頼者と僕が本当の話をするようになったら、裁判官は本当の話の方に共感してくれるようになった。そして、早くダルクに行けるように軽い判決を出してくれることもあった。ほんの少しだけ、刑事裁判が意味のあるものになってきた。
相変わらず、僕の依頼者の人たちに、僕の言葉はたいして響かない。
でもそれでいい。ダルクの仲間たちが会いに来てくれて、本当の話をしてくれる。
なんせ、僕の依頼者のことを仲間と呼んでくれるのだから。
僕の仕事は、ちょっぴり口下手な依頼者やその仲間たちの言葉を、裁判官に理解できる形に翻訳して、裁判官を説得することだけだ。ちょっとだけさみしい気がしないでもないけれど。
3.「ダメ、ゼッタイ」がはびこる社会の中で
子どものころから学校で、薬物を使えば人生が終わりだと教えられる。芸能人が大麻で捕まったら、大々的に報道されて、盛大にバッシングされる。多くの人がそれを正義だと思っている。でも、その正義の中に、今は使っていて、やめたいけど使いたくて苦しんでいる人たちや、やめてほしいと祈るように願っている家族の人たちへの視点はかけらもない。
世間は偏見で満ちあふれている。その中で生きていくのは、当事者も家族もしんどい。その風を受けている司法も偏見に満ちあふれている。
でも、ダルクの中にそんな偏見はない。みんな「仲間」だ。うまくいったりいかなかったりするけれど、みんな仲間として、お互いに必要とされている。
この、まだまだクソみたいな司法から少しでも早く解き放って、ダルクにつながってもらえるようにするのが僕の仕事だ。裁判官や検察官に、司法の中で僕たちにできることなんかないだろ?回復の邪魔すんなよ、と訴えかける。そして、不幸にも捕まった人に、世間は厳しいけれど、あなたに優しい場所もあるんだよ、こっちにこない?と誘ってみるのが僕の係だ。
世間から偏見がなくなって、刑罰で薬物の問題を解決しようなんて言う人がいなくなって、刑事弁護人として薬物依存症の人たちに関わる仕事なんてなくなればいいと、心から思う。でも、これがなくならないうちは、できるだけ多くの依存症の人と出会いたい。どれだけの人を司法から救いだしてこっちの世界に誘えるか、これからもやってみる。
本稿は、香川ダルクが2019年3月に発行したパンフレット「依存の反対語は『つながり』」に寄稿した文章を一部改編したものです。